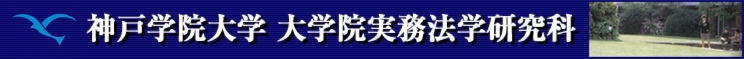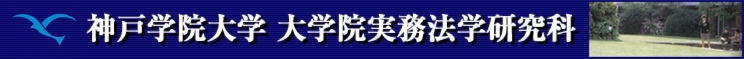| Q1 |
受験の年齢制限はありますか? |
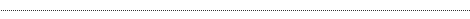 |
| A1 |
法科大学院の受験資格を満たす限り年齢制限はありません。 |
| |
|
| Q2 |
法科大学院適性試験は必ず受験しなくてはならないのですか? |
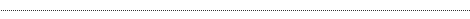 |
| A2 |
出願資格として、独立行政法人大学入試センターが実施する法科大学院適性試験または財団法人日弁連法務研究財団が実施する法科大学院統一適性試験の受験が必須となります。いずれの試験も受験できなかった場合は法科大学院への出願はできません。
|
| |
|
| Q3 |
法学専門試験はどのようなものになりますか? |
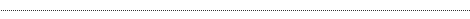 |
| A3 |
法学専門試験(法学既修者認定希望者のみ)は、憲法・民法・刑法の3科目と会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法の中から2科目選択の合計5科目についての基本的な事例問題や説明問題等を用いた論述試験です。標準3年の1年次修了と同程度の法的素養を持っているかどうかを確認するため、基礎的な法知識が正確に理解され、これを典型的な事例問題等に的確にあてはめ、理論的に証明・解法なしうるかが問われます。 |
| |
|
| Q4 |
特別評価項目の具体的な内容を教えてください。 |
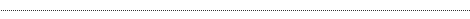 |
| A4 |
特別評価項目とは、入学志願者の資格取得や検定試験合格といった、目標を立て、努力・工夫し達成した実績に対し積極的な評価を行おうというものです。満点の10%を上限とし、複数項目に該当する方は別途上限までの範囲内でプラス評価を行います。
|
| |
|
| Q5 |
入学試験時に特別な優先枠などはありますか? |
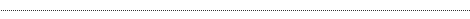 |
| A5 |
本学では入学試験時、優遇措置として社会人(有資格実務経験者)特別枠および特別評価項目を備え付けています。 |
| |
|
| Q6 |
社会人(有資格実務経験者)特別枠とはどういったものですか? |
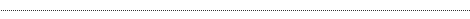 |
| A6 |
本学独自の入試制度である「社会人(有資格実務経験者)特別枠」は、一定の資格を用いた3年以上の実務経験を持つ人材を、前期試験で10名程度、後期試験では若干数を優先的に受け入れるというものです。以下が該当資格となります。
[社会人(有資格実務経験者)特別枠 該当資格]
公認会計士・司法書士・税理士・弁理士・医師・歯科医師・獣医師・薬剤師・管理栄養士・臨床心理士・社会福祉士・精神保健福祉士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・一級建築士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士・海事補佐人・海事代理士・外国での弁護士資格 |
| |
|
| Q7 |
社会人(有資格実務経験者)特別枠の実務経験とはどんなものですか? |
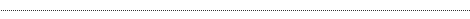 |
| A7 |
所持「資格につき3年以上の実務経験を有すること」とは、当該資格を有しなければその職務を遂行することができない必然性のある職責において、その資格に基づき行われた実務の経験を意味します。したがいまして、当該資格があるにこしたことはないが、なくても一般にその職務を遂行できる場合などは、ここに言う「資格につき3年以上の実務経験」には含まれません。なお、。実務経験を持たなくても、所持資格が特別評価項目に該当する場合には一定のプラス評価を行います(当該資格取得の証明となるものの写し等をご提出ください)。 |
| |
|
| Q1 |
法律を学んだことのない人でも講義についていけるのですか? |
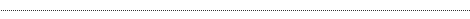 |
| A1 |
法科大学院の標準3年は、段階を踏んだ教育プロセスによって法学未修者でも課程修了時には法曹としての素養を十分に得ることができるよう、綿密にプランニングされています。したがって、次段階に進むまでに現段階での学習を十分に把握していれば、講義についていけないということはありません。 |
| |
|
| Q2 |
入学前に法学の勉強をしたほうがよいですか? |
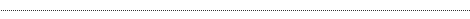 |
| A2 |
法曹への道をどうプランするかによります。ただ、入学前に法律を学んでおきたいとすれば、その学習目的を明確にして、それに見合った学習方法を選択してください。たとえば、2年コース進(入)学を目的とするのであれば、法学専門試験への対処として一定期間継続して集中的なトレーニングが必要となります。あるいは、スムーズな学習を目的とするのであれば、「まず大枠をつかみ、段階ごとに切り分けて理解を深め、これを何度も繰り返し思い起こす」という事前準備が有益です。法学、私法や刑事法などの入門書どれか一冊をじっくりと考えながら読んでください。 |
| |
|
| Q3 |
法科大学院で学習成果をあげるにはどうすれば良いですか? |
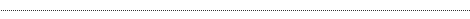 |
| A3 |
学習上の基本が2点あります。まずは、常日頃より、特定の目的を意識してそれを達成するために考えるという思考癖をつけることです。ルーティンな仕事(あるいは昼食のメニューの決定等)でも、その目的はいったい何であるのか、その目的のためにどのような工夫ができるのかを考えていただくことが大事です。次に、考えるときには“so
what,so why”(だからどうなの?どうしてなの?)という質問を繰り返してください。理論的に考える訓練です。 |
| |
|
| Q4 |
長期履修制度とはどのようなものですか? |
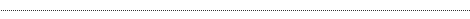 |
| A4 |
本学は昼間開講の法科大学院ですので、社会人が働きながら通うには時間的・労力的な面からも困難なものと思われます。そのため、原則3年の修学期間を、入学時に3年を超える履修計画を提出していただき、本学がこれを認めた場合は長期間での履修が可能となります。ただし、いったん許可された修業年限の事後の変更は認めません。 |
| |
|